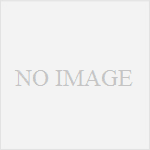1月下旬にT病院で検査を受ける事ができました。
腎生検と呼ばれる方法です。
背中から大きな針のような物を指して、腎臓に直接指して、腎臓の細胞を採取し、形状などを確認する方法です。
採取後、1週間ほど、傷口が塞がるまで入院する必要がありました。
もちろん24時間体制で身内が付き添いしなければならないので、クループ症候群でN病院に入院した時のように3交代制で妻と私と妻の両親で回しました。
腎生検をするにあたって、いろいろと説明されました。
あまりに体が小さく腎臓も小さいと背中を開いて腎臓から採取しないといけないそうですが、娘はぎりぎりそれをしなくてもなんとかやれる大きさだったようです。
ただ、やはり小さいと難易度が高いようで、4回も刺されたみたいでした。
まだ1歳の娘につらい思いをさせる事に複雑な気持ちでした。
検査後は、血尿が出る事もあるそうですが、ほとんどでず、順調に回復して退院できました。
その後、2週間程で、検査結果を聞く事ができました。
やはり、通常のステロイドが効くタイプのネフローゼ症候群ではない可能性が高く、詳しい病名はとりあえずびまん性メザンギウム硬化症と付けられました。
ただ、顕著に症状が出ているわけではなくその兆候があるという感じでした。
そして、次に遺伝子検査を勧められました。
親子で遺伝子検査をすると、その検査結果をもとに確度の高い治療ができる場合があるとの事でした。
迷わず遺伝子検査をする事に決めました。
する事は、血液を採取するだけで、それを神戸の大学病院に送って調べてもらいました。
こちらは、ネフローゼ症候群を遺伝的な見地から分類し、今後の治療に役立てるための情報収集のために国の予算でやっていたので、費用はかかりませんでした。
代わりに採取したデータは匿名で様々な研究や症例発表に使われるという事でしたが、匿名なので、気になりませんでした。
遺伝子検査の結果が出るまでに2~3か月かかるとの事で、それまでは病気の進行を遅らせる対処療法的に投薬をする事になりました。
血圧を下げる薬と、血液をサラサラにする薬。
それから、甲状腺ホルモンも蛋白なので、尿に流れ出ていてバランスが崩れているとの事で、こちらも投薬で調整する事に。
さらに、合併症で目や耳に障害が出る可能性があるとの事で、一応眼科と耳鼻科で検査してもらってくださいとの事でした。
眼科は、同じT病院の眼科を受ける事にしましたが、耳鼻科はまだ意思表示のできない娘はより専門設備がないとできないとの事で、普段通っていた療育センターでする事にしました。